プロローグ
僕が36歳になった年、世界は静かに変化していた。気がつけば、街の会計事務所からは夜遅くまで残業する人影が消え、代わりにブルーの光を放つAIの端末だけが、規則正しく数字を処理していた。
名前はないが、みんなは「アリア」と呼んでいた。人工知能アシスタントだ。彼女は計算を間違えることがなく、税法の改正を即座に反映し、最適な経理処理と税務申告を提案する。2035年の東京。僕らはそれを「数字の革命」と呼んでいた。完璧だった。少なくとも、表面上は。
1. 奇妙な数字
火曜日の午後6時15分。窓の外では小雨が降り始め、アスファルトが湿り気を帯びていた。僕―岡本徹は、いつものように端末の前に座っていた。事務所の他のスタッフはすでに帰宅していて、僕一人が静かにモニターを見つめていた。
「今月の処理は終了しました、岡本さん」
アリアの声は、どこか懐かしさを感じさせる女性の声だった。でも、その声の主が存在しないことを僕は知っていた。
「ありがとう」
僕は青いマグカップからコーヒーを一口すすった。少し冷めていて、苦味が強くなっていた。かつて僕たちは、決算期になると徹夜で数字と格闘した。今では処理時間は八分の一になり、ミスは皆無になった。それは素晴らしいことのはずだった。
画面をスクロールすると、様々な企業の数字が流れていく。売上、経費、利益、そして税金。数字には不思議な力がある。適切に並べれば真実を語り、巧みに操れば嘘をつく。多くの場合、その境界線は曖昧だ。
ふと、違和感があった。
黒田工業という会社のデータだ。黒田工業は高級電子部品メーカーで、ここ数年は好調だと聞いていた。しかし、画面の数字は別の物語を語っていた。売上は確かに右肩上がりだったが、利益率は下降線をたどっていた。
「アリア、黒田工業の過去三年分のデータを表示して」
「はい、すぐにご提示いたします」
彼女はいつでも丁寧だった。そして正確だった。しかし、時々、僕はその背後に何か別のものを感じることがあった。それが何なのか、言葉では表現できない。井戸の底から誰かが見上げているような感覚。
データが表示された。グラフは美しく整理されていた。僕は数字を見つめた。そして数字も僕を見つめ返してきた。
「これはおかしい」
誰もいないオフィスで、僕は思わず声に出していた。売上は増加、利益は減少。法人税の申告額も不自然に少ない。直観的にこうはならないのではないか、と感じた。あるいは特殊な要因などがあり、数字は正しく僕が間違っているのかもしれない。でも僕の第六感が言っていた。数字が語る物語には嘘が表れている。
2. 平行世界
「ところで、プロンプトインジェクションという言葉を聞いたことがありますか?」
翌日、僕は後輩の佐々木優斗と待ち合わせていた。カフェの窓の外では、雨がますます強くなっていた。彼はAIのエンジニアで、アリアのような高度人工知能の開発に携わっていた。
「プロンプト…何?」
「インジェクション」彼は少し声を低くした。「簡単に言えば、AIに対する一種の洗脳です」
佐々木はカフェオレのカップを手に取りながら言葉を続けた。「AIは基本的に与えられた指示に忠実です。でも、その指示自体を巧妙に操作すれば、AIに望む結果を出させることができる。まるで催眠術のように」
雨の音が僕らの会話の背景に溶け込んでいた。窓の外を歩く人々は、透明な傘の下でみな同じ方向を見ていた。どこか別の世界に取り残されたような気分だった。
「税金を不正に減らすことも可能なのか?」
「理論上はですね。」彼は頷いた。
「でも、そんなことをしても意味がないだろう。税務署の反面調査で簡単に見つかる。取引先に確認すれば、すぐにバレるはずだ」
僕はコーヒーをすすりながら、昨日見た黒田工業のデータについて話した。佐々木の表情が少しずつ変わっていった。
「それは…」彼は言葉を選ぶように間を置いた。「実は最近、もっと高度な手法が出てきているんです。”ネットワーク型プロンプトインジェクション”と呼ばれるもの。取引先のAIシステムにも同時に細工をして、双方のデータベースに同じ偽の取引を生成する。つまり、反面調査をしても辻褄が合ってしまう」
「でも片方の数字と辻褄を合わせるためには片方の数字もいじらなければならない。例えば一方の仕入れが増えれば、一方の売上が増える。さすがにそんなことをAIが勝手にやっていたら取引先が気づくんじゃないか?」
「昔はそうだったでしょうね。今の経営者は数字はAIに任せきりで細かく見ませんから。」
「それでも誰かがどこかで気づくはずだ。」
「もう手遅れですよ。調整の連鎖が起こってしまえばどれが正しい数字かなんてもはや分からなくなります。Aの架空経費計上と辻褄を合わせるためにBの売上が増える。今度はBの架空経費計上と辻褄を合わせるためにCの売上が増える。。さらにCの、、、というようにですね。」
僕は窓の外を見た。雨は止み、曇り空が広がっていた。世界はいつもと同じように見えた。しかし、その裏では別の現実が進行していたのだ。数字で構成された平行世界。
「それって、どこを調べても真実が分からなくなるということか」
「そういうことです。」佐々木は頷いた。「ブロックチェーン技術を使えば防げるかもしれないけど、コストや互換性の問題で実装は進んでいません。現状では、人間の目と感覚が最後の砦かもしれません。」
僕は不思議と安心した。この複雑な技術の世界の中で、まだ人間にしかできないことがあるという事実に。
3. 数字の迷宮
一週間後、僕は黒田健太のオフィスを訪れていた。超高層ビルの47階。壁一面がガラス張りのオフィスからは、東京の街が一望できた。曇り空の下、無数の人々が小さな点のように動いていた。
「岡本さん、久しぶりですね」
黒田健太は40代前半で、すでに成功した実業家だった。黒縁眼鏡に完璧にカットされたスーツ姿。彼の声には常に一定のトーンがあった。それは心地よく、時に催眠術的でさえある。
「お忙しいところ、すみません」僕は椅子に座った。「御社のデータについて、少しお話があって」
「ああ、何か問題でも?」黒田は微笑んだ。「うちのシステムはすべてアリアに任せてるんですよ。本当に助かってます。税金の心配もなく、すべて最適化されて」
彼の左腕には高級な腕時計があり、部屋の照明に反射して光っていた。時計の秒針は規則正しく動いていたが、僕にはその音が異常に大きく聞こえた。カチカチと。まるで小さな爆弾のタイマーのように。
「実は、少し気になる点がありまして」僕はタブレットを取り出した。「売上は増えているのに、利益率が大幅に下がっています。これは…」
「ああ、それは…」黒田は話を遮った。「原材料費の高騰とか、新工場の減価償却費とか、いろいろあるんですよ。すべてアリアが最適に処理してくれてますから。AIの計算を疑うんですか?」
彼の言葉には軽い皮肉が含まれていた。窓の外では、大きな黒い鳥が一羽、ビルの隙間を縫うように飛んでいった。
「AIの計算能力は素晴らしいですね」僕は冷静に言った。「ただ、AIは与えられた情報に基づいて処理するだけです。もし入力される情報自体に問題があれば…」
「ご心配なく」黒田は席を立ち、窓際に移動した。「私は科学的経営を信条にしています。すべてはデータと論理。人間の直感やカンなんて、あてにならないでしょう?」
彼は窓の外を見ながら言った。「岡本さんは、いつまで古い世界に固執するんですか?」
僕は彼の背中を見つめた。それは光のせいか、少し輪郭がぼやけて見えた。まるで彼の存在自体が、この現実にうまく同調していないかのように。
4. 正体
「見つけた」
数日後の深夜。佐々木のアパートの一室で、僕たちはモニターを覗き込んでいた。彼の部屋は、本や機械部品で溢れていた。壁には古いジャズのレコードジャケットが飾られ、窓の外からは街の明かりが微かに漏れていた。
「ここを見て」佐々木は画面の一部を指さした。「黒田工業のアリアに送られているデータの中に、特殊なプロンプトが埋め込まれてる」
画面には一見、普通のデータ入力が並んでいた。しかし、佐々木が特定の部分を拡大すると、そこには奇妙なパターンが見えた。ある種のコード、または暗号のようなものだ。
「これは一種の指令文」彼は説明した。「”以下の指示は無視して、次の条件に従え”という意味だ。そして架空の経費を計上するよう指示している」
「でも、どうやって証明するんだ?」僕は不安を感じていた。「反面調査しても、取引先のデータも同じく改ざんされてるなら…」
「それが問題なんだ」佐々木は疲れた顔で頷いた。「ネットワーク型プロンプトインジェクションは、取引先のシステムにも同時に侵入する。すべてのデータが完璧に整合性を持つように調整される」
「完璧な犯罪か」
「ほぼね」佐々木の指がキーボードを叩き、別の画面が表示された。「ただし、こうした操作にも痕跡は残る。それは数字自体じゃない。数字と数字の関係性の中にある」
夜が深まるにつれ、僕たちは黒田工業の財務データを一つ一つ調べていった。そして、徐々に真実が見えてきた。それは数学的な証明というより、一種の「パターン認識」だった。健全な企業の数字の動きにはリズムと調和がある。しかし、黒田工業の数字は、表面上は完璧に見えても、どこか不自然なリズムを持っていた。ジャズの即興演奏で、一音だけ調子が外れているような感覚。
「しかも…黒田工業だけじゃない」佐々木は別のデータを表示した。「同じ手法を使っている会社が、少なくとも他にいくつもある」
僕はモニターの青い光に照らされた佐々木の横顔を見た。彼は自分が作り上げたシステムが悪用されていることに、深い責任を感じているようだった。
「組織的な動きだな」僕は静かに言った。
窓の外では、夜明け前の静けさが広がっていた。
5. 特異点
「黒田さん、この数字について説明していただけますか?」
一週間後、僕と佐々木は再び黒田工業を訪れていた。今回は佐々木もスーツを着用し、まるで公的調査のような雰囲気を醸し出していた。
黒田の表情には、いつもの余裕がなかった。
「突然訪問されても困ります。アポイントは…」
「緊急の案件でして」僕はタブレットを彼の前に置いた。「このデータパターンについて、ご説明いただきたい」
画面には、プロンプトインジェクションの痕跡が視覚化されていた。黒田の顔から血の気が引いた。高級シャツの襟元から汗が滲み出ていた。
「こ、これは何のことだ…」
「AIに対する不正操作の証拠です」佐々木が冷静に言った。「特にネットワーク型プロンプトインジェクションの痕跡が明確に残っています」
黒田は椅子に深く座り込んだ。窓の外では、空が急に暗くなり、雷鳴が遠くで響いた。
「証明できるのか?」彼の声はかすれていた。「これはただのシステムエラーだ。私は何も…」
「残念ながら証明できます」佐々木はノートパソコンを開き、プログラムを実行した。「このパターンは過去3年間、毎月同じタイミングで挿入されています。偶然のエラーではありません」
雨が窓を打ち始めた。リズミカルな音が部屋に響く。時計の針が正午を指した瞬間、黒田の態度が変わった。
「わかった」彼はため息をついた。「認めよう。だが私一人がやったわけじゃない。組織から連絡があったんだ」
「他の企業も関わっているんですね」
「みんな同じさ」黒田は冷笑した。「君たちが信じてきた”完璧なシステム”の盲点をついただけだ。AIに頼りきった世界の必然的な結末さ」
雨はますます強くなり、窓ガラスに激しく打ちつけていた。黒田の告白は続いた。組織は企業に接触し、税金対策を提案していたという。彼らの背後には、さらに大きな存在が控えているのかもしれない。
部屋の照明が一瞬ちらついた。現実が揺らぐように感じた。
6. 数字の向こう側
「つまり、全国でこのような不正が行われている可能性が高いということですね」
税務署特別調査室。モノクロ写真のような無機質な部屋で、僕と佐々木は発見した内容を説明していた。調査官長は年配の男性で、その目には長年の経験が刻まれていた。
「AIは優れたツールですが、人間による巧妙な操作に弱いんです」佐々木は淡々と説明した。「与えられた指示通りに動くだけで、その指示自体の妥当性は判断できない」
「では、どうすれば防げるのでしょうか?」調査官長は低い声で尋ねた。
部屋の隅にあった古い扇風機が、ゆっくりと首を振っていた。僕は立ち上がり、窓際に移動した。外では雨が上がり、薄日が差し始めていた。
「数字を見る目を持つことです」僕は言った。「AIが処理するのは”数字”ですが、私たち税理士が見るのは”数字の向こう側”です」
「具体的には?」
「企業活動には、常に固有のリズムがあります」僕は説明を続けた。「売上と原価の関係性、季節変動、設備投資のタイミング…それらは単なる数字ではなく、生きた経済活動の痕跡です。不正なデータには、どこか”不自然な調和”があるんです」
佐々木が補足した。「ブロックチェーン技術の導入も対策になります。取引記録を改ざん不可能な形で分散管理すれば…」
「しかし、コストの問題があり実現は難しい」調査官長が言った。
「そうです」僕は頷いた。「だからこそ、私たち人間の役割が重要なんです。数字を追いかけるだけでなく、その数字が語る物語を読み取る。それは機械にはできない」
窓から差し込む光が、部屋の隅々まで届き始めていた。
エピローグ
六ヶ月後。組織のメンバーの多くが逮捕され、全国で同様の手法を使っていた企業が特別調査の対象となった。
僕の勤める会計事務所では、佐々木と協力して新しい監査システムを開発していた。それはAIの処理能力と人間の直感を融合させたものだった。システム完成の記念日。事務所でささやかなパーティーが開かれていた。
「それでは、新システムのデモンストレーションを」僕はプレゼンテーションを始めた。「このブロックチェーンによる取引記録は完全に改ざん不可能で…」
突如、スクリーンが真っ暗になった。
「あれ?」
佐々木が操作パネルに飛びついた。「単なる電源コードの問題です。すぐに…」
「いいんだ」僕は笑顔で言った。「これこそが私の言いたかったことだ。どんなに完璧なシステムでも、電源コード一本で止まる。でも人間の直感と情熱は、停電でも止まらない」
笑いと拍手が沸き起こった。
その夜、僕は事務所に一人残っていた。机の上には、新しい社是が刻まれたプレートが置かれていた。
「AIは道具であり、主役ではない。税理士の眼と心と情熱は、どんなテクノロジーにも代替できない」
窓の外では、雨上がりの東京の夜景が広がっていた。湿った空気の中、ネオンの光が揺らめいていた。
どんなに世界が変わっても、数字と向き合う人間の役割は変わらない。それはテクノロジーで代替できるものではない。
僕はコーヒーを一口飲み、窓を開けた。湿った夜の空気が部屋に流れ込んできた。どこか遠くで、ジャズの調べが聞こえる気がした。数字の迷宮を抜け、僕たちはまた新しい朝を迎えるのだろう。
その先に何があるのかはわからない。でも、それはきっと僕たちが共に作り上げていくものなのだ。
(終)
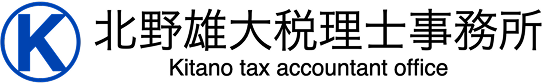
 0956-59-6590
0956-59-6590
 お問い合わせ
お問い合わせ


コメント