こんにちは。税理士の北野です。
経営者の皆様は、日々会社の業績を気にかけていらっしゃることと思います。
特に毎月の売上は、最も分かりやすい指標として、一喜一憂されている方も多いのではないでしょうか。
しかし、毎月の売上だけを追うのは、いわば健康管理で「体重」だけを見ているようなものです 。
本当に健康な状態かを知るためには、体重だけでなく、「血圧(=安全性)」 や「筋肉量(=生産性)」 など、体の内部まで詳しく見る必要があります。
経営も同じです。
経営指標というツールを使えば、会社の内部まで詳しく知ることができ 、今までなんとなく「調子が良い」「悪い」と感じていた部分が、具体的な数字として明確になります 。
今回のブログでは、会社の経営状態を多角的に分析するための代表的な経営指標を「収益性」「安全性」「生産性」「成長性」の4つのカテゴリーに分けて、網羅的にご紹介します 。
ぜひ、ご自身の会社の「健康診断」を行うつもりで読み進めてみてください。
第1章:収益性分析 ~会社の「稼ぐ力」を測る~
まずは、会社の最も基本的な力である「稼ぐ力(=収益性)」を分析する指標です 。商品やサービスがどれだけの利益を生み出しているのか、資産を効率的に使えているのかを見ていきましょう。
売上高総利益率(粗利率)
- 計算式: 売上高総利益率(%)=(売上総利益÷売上高)×100
(※売上総利益 = 売上高 – 売上原価) - 概要: 売上高に占める売上総利益(粗利)の割合を示す指標で、「粗利率(あらりりつ)」とも呼ばれます 。会社が提供する商品やサービスの基本的な収益力を表します 。
- ポイント: この比率が高いほど、原価に対して高い価格で販売できている、つまり「儲けの大きい」商売をしていることになります 。業種によって平均値は大きく異なります 。
営業利益率
- 計算式: 営業利益率(%)=(営業利益÷売上高)×100
(※営業利益 = 売上総利益 – 販売費及び一般管理費) - 概要: 売上高に占める営業利益の割合を示す指標です 。会社が本業でどれだけ効率的に稼いでいるかを表します 。
- ポイント: 営業利益は、粗利から広告宣伝費や人件費などの経費を差し引いたものです 。この比率が高いほど、本業の収益性が高く、競争力があると言えます 。
損益分岐点売上高
- 計算式: 損益分岐点売上高=固定費÷限界利益率
(※限界利益率 = 限界利益 ÷ 売上高)
(※限界利益 = 売上高 – 変動費) - 概要: 利益がゼロになる売上高のことで、赤字でも黒字でもない、ちょうどトントンになる状態を指します 。
- ポイント: 損益分岐点を把握することで、「あとどれくらい売上が必要か」や「どこまで経費を削減すべきか」といった具体的な目標設定に役立ちます 。経営の安全性を測る重要な指標です 。
ROA(総資産利益率)
- 計算式: ROA(%)=(当期純利益÷総資産)×100
- 概要: ROA (Return On Assets)は、会社が持つ全ての資産(総資産)を使って、どれだけ効率的に利益を生み出しているかを示す指標です 。
- ポイント: ROAが高いほど、資産を有効活用して効率よく稼いでいる「やりくり上手な会社」と言えます 。銀行からの借入金など、他人資本も含めた全ての資産を対象としているのが特徴です 。
ROE(自己資本利益率)
- 計算式: ROE(%)=(当期純利益÷自己資本)×100
- 概要: ROE (Return On Equity)は、株主が出資したお金(自己資本)を使って、どれだけ効率的に利益を生み出しているかを示す指標です 。「自己資本利益率」とも呼ばれ、特に株主が重視する指標です 。
- ポイント: ROEが高いほど、株主のお金を元手に効率よく稼いでいることを意味し、投資家にとって魅力的な会社と評価されます 。
総資産回転率
- 計算式: 総資産回転率=売上高÷総資産
- 概要: 会社が持つ総資産を、年間で何回売上に変えられたかを示す指標です 。資産をどれだけ活発に事業活動へ投入できているか、その効率性を測ります 。
- ポイント: この回転率が高いほど、少ない資産で大きな売上を生み出しており、資産を効率的に活用できていると評価されます 。「薄利多売」のビジネスモデルの会社は、この数値が高くなる傾向があります 。
売上債権回転期間
- 計算式: 売上債権回転期間(月)=売上債権÷(売上高÷12)
(※売上債権 = 売掛金 + 受取手形) - 概要: 商品やサービスを販売してから、その代金(売掛金や受取手形)を回収するまでに平均でどのくらいの期間がかかるかを示す指標です 。
- ポイント: この期間が短いほど、売上の現金化が早く、資金繰りが健全であると評価されます 。逆に長すぎると、貸し倒れのリスクや、運転資金が不足する可能性が高まります 。
第2章:安全性分析 ~会社の「体力・抵抗力」を測る~
次に、会社の支払い能力や倒産リスクなど、財務的な「安全性」を分析する指標です 。短期的な資金繰りから長期的な安定性まで、会社の体力をチェックしましょう。
流動比率
- 計算式: 流動比率(%)=(流動資産÷流動負債)×100
- 概要: 短期的な支払い能力を測るための最も代表的な指標です 。1年以内に現金化できる資産(流動資産)が、1年以内に支払うべき負債(流動負債)をどれだけ上回っているかを示します 。
- ポイント: この比率が高いほど、短期的な資金繰りに余裕があることを意味します 。一般的に200%以上あると安全とされ、100%を下回ると支払い能力に懸念があると見なされます 。
当座比率
- 計算式: 当座比率(%)=(当座資産÷流動負債)×100
- 概要: 流動比率よりもさらに厳しく短期的な支払い能力を測る指標です 。流動資産の中でも、特に現金化しやすい資産(当座資産)だけで、流動負債をどれだけカバーできるかを示します 。
- ポイント: 在庫(棚卸資産)はすぐに現金化できるとは限らないため、それを除いて計算します 。これにより、より現実的な支払い能力が分かります 。一般的に100%以上あれば安全とされています 。
手元流動性比率
- 計算式: 手元流動性比率(ヶ月)=現預金÷月商(年間売上÷12)
- 概要: 企業が月々の売上の何ヶ月分の現預金を持っているかを示す指標で、不測の事態に対する支払い能力を測ります 。
- ポイント: この比率が高いほど、急な支払いが発生したり、売上が落ち込んだりしても耐えられる体力があることを示します 。最低でも1ヶ月分、中小企業であれば1.5ヶ月分以上あると安心とされています 。
固定比率
- 計算式: 固定比率(%)=(固定資産÷自己資本)×100
- 概要: 設備投資などの長期的な資産(固定資産)が、返済不要の自己資本でどれだけ賄われているかを示す指標です 。長期的な財務の安定性を測ります 。
- ポイント: 土地や建物などの固定資産はすぐに現金化できないため、返済義務のある負債ではなく、安定した自己資本で調達しているのが理想です 。この比率が100%以下であることが望ましいとされます 。
固定長期適合率
- 計算式: 固定長期適合率(%)={固定資産÷(自己資本+固定負債)}×100
- 概要: 固定比率を少し緩やかにした指標です 。固定資産が、自己資本と返済期間の長い固定負債でどれだけ賄われているかを示します 。
- ポイント: 長期的な借入金(固定負債)も固定資産の購入資金に充てられることを考慮した指標です 。この比率も100%以下であることが、長期的に安定している目安となります 。
負債比率
- 計算式: 負債比率(%)=(負債合計÷自己資本)×100
- 概要: 返済不要の自己資本に対して、返済義務のある負債(他人資本)がどれくらいの割合かを示す指標です 。
- ポイント: この比率が低いほど、借金が少なく財務的に安定していることを意味します 。一般的に100%以下だと理想的とされます 。
自己資本比率
- 計算式: 自己資本比率(%)=(自己資本÷総資産)×100
- 概要: 会社の総資産のうち、返済不要の自己資本がどれくらいの割合を占めるかを示す、最も重要な安全性指標の一つです 。
- ポイント: この比率が高いほど、借金に頼らない安定した経営ができている「筋肉質な会社」と言えます 。倒産しにくい会社の目安として、最低でも30%以上、50%以上あれば非常に優良と評価されます 。
借入金依存度
- 計算式: 借入金依存度(%)=(借入金合計÷総資産)×100
- 概要: 会社の総資産のうち、どれくらいを借入金(短期・長期)で賄っているかを示す指標です 。
- ポイント: この比率が高いと、金利の支払いが経営を圧迫したり、新たな融資を受けにくくなったりする可能性があります 。業界によりますが、通常50~60%までが許容範囲で、70%を超えれば要警戒といえます 。
第3章:生産性分析 ~人・モノ・金の「効率」を測る~
ここでは、投下した経営資源(従業員や設備など)から、どれほどの価値を生み出せたかという「生産性」を分析する指標をご紹介します 。
付加価値額
- 計算式: 付加価値額=売上高−外部購入費用(材料費、外注費など)
または 付加価値額=経常利益+労務費+人件費+金融費用+賃借料+租税公課+減価償却費 - 概要: 企業が事業活動を通じて新しく生み出した価値の大きさを示す金額です 。簡単に言うと、「仕入れたモノやサービスに、どれだけの価値を上乗せして販売したか」という、その企業の儲けの源泉です 。
- ポイント: この付加価値額が、従業員の給料、会社の利益、税金などの源泉となります 。付加価値額が大きいほど、社会に多くの価値を提供している企業と言えます 。
付加価値率
- 計算式: 付加価値率(%)=(付加価値額÷売上高)×100
- 概要: 売上高に対して付加価値額がどれくらいの割合を占めるかを示す指標です 。企業の収益性の高さを表します 。
- ポイント: この比率が高いほど、自社の活動で多くの価値を生み出していることを意味します 。利益率の高いビジネスモデルの会社は、この数値が高くなる傾向があります 。
労働分配率
- 計算式: 労働分配率(%)=(人件費÷付加価値額)×100
- 概要: 生み出した付加価値が、どれだけ従業員の給料(人件費)として分配されたかを示す割合です 。
- ポイント: この比率が高すぎると会社の利益を圧迫し、低すぎると従業員への還元が不十分で士気の低下につながります 。経営者と従業員のバランスを示す指標と言えます 。
労働生産性
- 計算式: 労働生産性=付加価値額÷従業員数
- 概要: 従業員一人当たりがどれだけの付加価値を生み出しているかを示す指標です 。従業員の働きぶりの効率性を測ります 。
- ポイント: 労働生産性が高いほど、少ない人数で効率的に価値を生み出していることになり、企業の競争力が高いと評価されます 。企業の成長のために非常に重要な指標です 。
一人あたり売上高
- 計算式: 一人あたり売上高=売上高÷従業員数
- 概要: 従業員一人当たりがどれだけの売上を上げているかを示す指標です 。労働生産性が「価値」を基準にするのに対し、こちらは「売上」を基準にしています 。
- ポイント: 従業員一人ひとりの活動がどれだけ売上に貢献しているかを示します 。労働生産性と合わせて見ることで、「売上は大きいが、利益(付加価値)は少ない」といった企業体質を分析できます 。
設備生産性
- 計算式: 設備生産性=付加価値額÷有形固定資産
- 概要: 工場や機械などの設備(有形固定資産)が、どれだけ効率的に付加価値を生み出しているかを示す指標です 。
- ポイント: この数値が高いほど、設備への投資がうまく付加価値に結びついていることを意味します 。特に製造業など、大規模な設備を必要とする業種で重要視されます 。
第4章:成長性分析 ~会社の「将来性」を測る~
最後に、「企業がどれだけ成長してきたか」、また「今後の成長可能性がどれくらいか」といった「成長性」を分析するための指標です 。
過去の実績から未来の可能性を探ります。
売上高成長率(増収率)
- 計算式: 売上高成長率(%)={(当期の売上高−前期の売上高)÷前期の売上高}×100
- 概要: 去年に比べて売上高がどれだけ伸びたかを示す指標です 。「増収率」とも呼ばれ、企業の事業規模の拡大スピードを表します 。
- ポイント: この比率が高いほど、提供している商品やサービスの需要が伸びており、会社が勢いよく成長していることを示します 。市場シェアが拡大しているかどうかの目安にもなります 。
経常利益成長率
- 計算式: 経常利益成長率(%)={(当期の経常利益−前期の経常利益)÷前期の経常利益}×100
- 概要: 去年に比べて経常利益がどれだけ伸びたかを示す指標です 。企業が本業と財務活動を合わせて稼ぐ実力がどれだけ成長しているかを表します 。
- ポイント: 売上高成長率と合わせて見ることが重要です 。売上が伸びていても、利益の成長が伴っていなければ、「儲からない忙しさ」に陥っている可能性があります 。
総資本成長率
- 計算式: 総資本成長率(%)={(当期末の総資本−前期末の総資本)÷前期末の総資本}×100
(※総資本 = 貸借対照表の負債の部と純資産の部の合計) - 概要: 去年に比べて総資本(総資産)がどれだけ増加したかを示す指標です 。会社全体の規模がどれだけ大きくなったかを総合的に判断するために使います 。
- ポイント: 成長のための投資が積極的に行われているかを示唆します 。ただし、借入金の増加も含まれるため、中身の確認は必要です 。
純資産増加率
- 計算式: 純資産増加率(%)={(当期末の純資産−前期末の純資産)÷前期末の純資産}×100
- 概要: 去年に比べて純資産(自己資本)がどれだけ増えたかを示す指標です 。企業の内部留保(利益の蓄積)が進み、企業の体力がどれだけ増強されたかを表します 。
- ポイント: 借金ではない「自分のお金」である純資産が増えることは、企業の財務的な安定性が高まっていることを意味します 。持続的な成長のためには、この指標の向上が不可欠です 。
一株当たり当期純利益(EPS)
- 計算式: EPS(円)=当期純利益÷発行済株式総数
- 概要: EPS (Earnings Per Share)は、株式一株に対してどれだけの当期純利益を生み出したかを示す指標です 。株主にとって最も重要な指標の一つで、企業の収益力と株主への還元力を測るものです 。
- ポイント: EPSが高いほど、その株式は「稼ぐ力が強い」と評価されます 。また、EPSが年々成長している企業は、株主価値を高めていると見なされ、投資家からの人気が高まる傾向があります 。
まとめ
今回は、会社の経営状態を客観的に把握するための様々な経営指標をご紹介しました。
これらの指標を計算し、分析することで、自社の「健康状態」を多角的に理解することができます。
大切なのは、一度計算して終わりにするのではなく、定期的にこれらの数値をチェックし、時系列での変化を追いかけていくことです。
そうすることで、経営改善のための具体的な課題や、次の一手が見えてくるはずです。
「自社の決算書から、どの数字をどう見ればいいのか分からない」
「指標を計算してみたが、自社の業界の平均と比べてどうなのか知りたい」
もし、そのようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひご相談ください。
皆様の会社の健全な成長をサポートさせていただきます。
弊事務所の対応地域
訪問可 :長崎県佐世保市、佐々町、旧北松地区、松浦市、平戸市
オンライン:全国
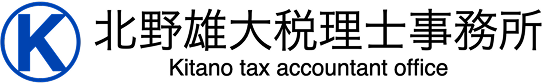
 0956-59-6590
0956-59-6590
 お問い合わせ
お問い合わせ
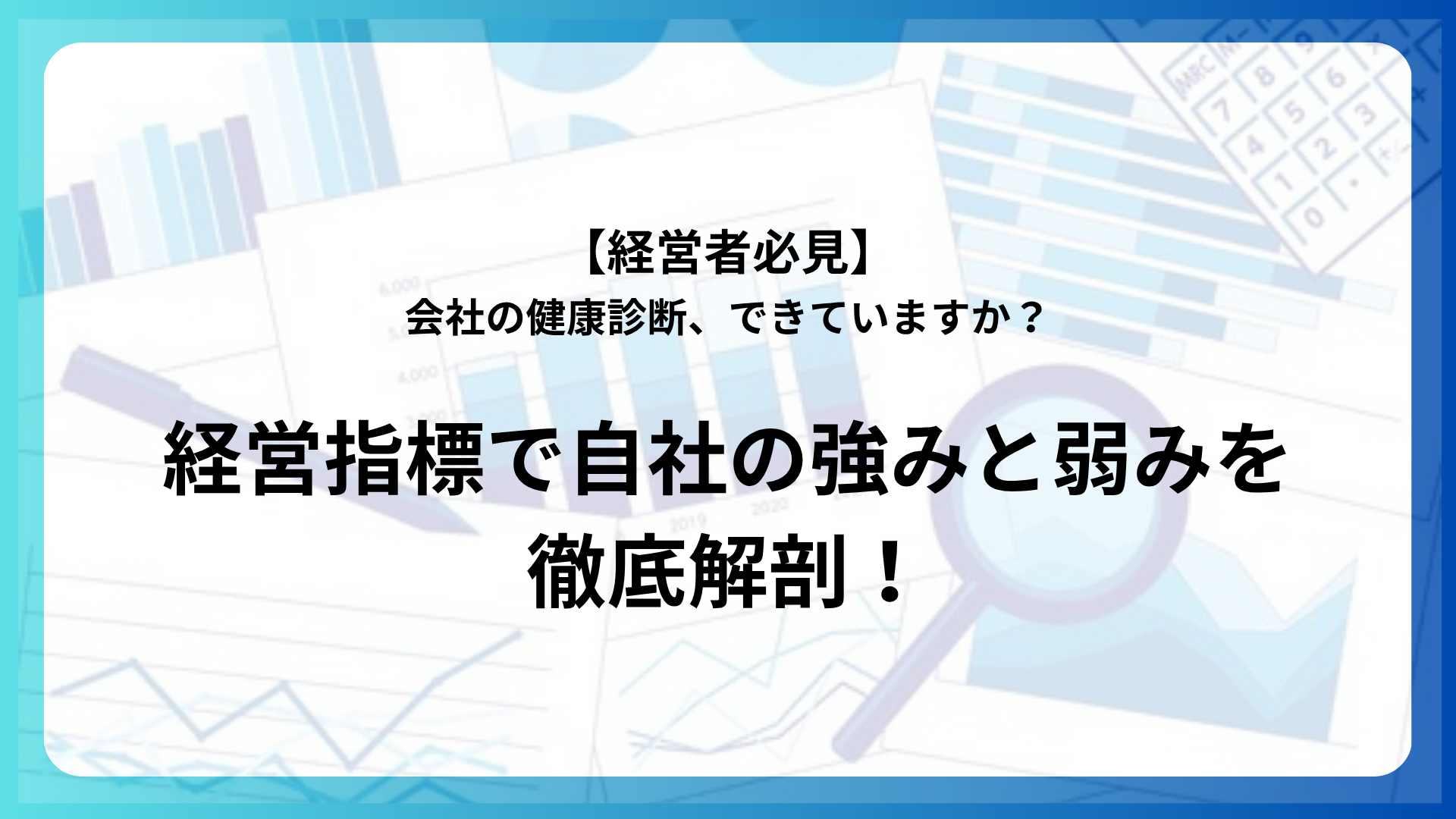
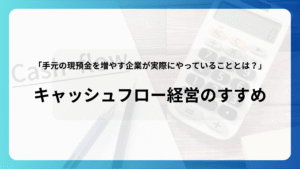
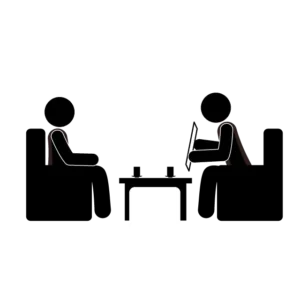

コメント