小規模企業共済
経営者のための「節税」と「退職金」を両立する最強の制度
国の機関である中小機構が運営する、小規模企業の経営者や役員、
個人事業主のための退職金制度。その強力な節税メリットと、
将来の資産形成について詳しく解説します。
もし、あなたの課税所得600万円なら…
年間 25.2万円
税負担が軽くなります。
これは、毎月最大の7万円を拠出した場合の所得税・住民税の軽減額の目安です。
掛金が全額「所得控除」となるため、これほどの節税効果が生まれます。
仕組み①:掛金が「全額所得控除」になる
所得税は、所得全体から各種「所得控除」を差し引いた後の「課税所得」に税率を掛けて計算されます。
小規模企業共済の掛金は、この所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象です。
支払った掛金の全額が課税対象から外れるため、特に所得が高い方ほど大きな節税効果が期待できます。
課税所得600万円の場合、年間掛金84万円が全額控除され、最終的な課税所得は516万円に圧縮。
この差額に税率を掛けた分だけ、税金が安くなります。
仕組み②:受取時の税金が優遇される
将来、共済金を一時金で受け取る際は「退職所得」扱いとなり、給与所得など他の所得と分離して税額が計算されます。
この際に適用される「退職所得控除」が非常に強力で、税負担を大幅に軽減します。
【受取額の目安】
中小機構の規定では、掛金月額7万円を20年(240か月)継続した場合の基本共済金(共済金B)は17,929,800円です。
これに国の運用実績に応じた付加共済金が加算されます。
受取共済金額
約 1,800万円
退職所得控除後
1,000万円
最終的な課税所得
500万円
【計算式】
( 受取額 1,800万円 – 退職所得控除 800万円 ) × 1/2 = 500万円
※退職所得控除額 = 40万円 × 掛金納付期間20年 = 800万円
4つの受取ケーススタディ
ケース1:老齢給付(共済金B)
45歳役員が20年間拠出し、65歳で老齢給付を受給。
掛金納付期間15年以上、65歳以上で受け取れる一般的な退職金です。
税負担の軽減額
約 520万円 お得
(同額を給与等で受け取る場合との比較)
ケース2:法人成り(共済金B等)
35歳個人事業主が10年間拠出し、45歳で法人成り。
個人事業を法人化した場合に受け取れる共済金です。
税負担の軽減額
約 191万円 お得
(同額を給与等で受け取る場合との比較)
ケース3:短期任意解約
40歳役員が5年間で任意解約。
掛金納付月数が240か月(20年)未満の任意解約は元本割れします。
20年以上の掛金納付期間があれば、任意解約でも元本割れはしません。
元本割れ
– 84万円
ケース4:長期任意解約
40歳役員が30年間拠出し、70歳で任意解約。
長期継続により、任意解約でも受取額は掛金総額を大幅に上回り、
退職所得控除額も大きくなります。
税負担の軽減額
約 1,008万円 お得
(同額を給与等で受け取る場合との比較)
隠れたメリット:低金利の貸付制度
小規模企業共済は、将来の退職金だけでなく、現在の事業資金を支える「セーフティネット」としての機能も備えています。
積み立てた掛金の範囲内で、無担保・無保証人で事業資金の貸付けを受けることができます。
共済を解約することなく資金調達ができるため、節税メリットや将来の退職金を維持したまま、急な資金需要に対応できます。
【一般貸付制度の活用例】
掛金7万円を5年間継続(納付総額420万円)している事業者が、
急な設備投資で300万円必要になった場合…
借入可能額の目安
〜300万円
利率(年利)
1.5%
審査・手続き
迅速
※借入額や利率は貸付制度の種類や経済情勢により変動します。
なぜ受取額が掛金総額を上回るのか?
「付加共済金」の仕組み
原資は国の資産運用益
加入者から集めた掛金の積立金を、国(中小機構)が法律に基づき、安全かつ効率的に運用して得た利益が原資となります。
金額は毎年変動(非保証)
毎年度の運用実績に応じて、経済産業大臣が支給率を定めます。そのため、金額は毎年変動し、将来の受取額が保証されるものではありません。(近年の支給率は0%〜0.1%程度で推移)
毎年少しずつ積み増される
毎年度末の基本共済金額に、その年度の支給率を掛けて計算された額が、毎年少しずつ積み増されていきます。長期加入ほど複利効果が期待できます。
⚠️ 制度利用の重要ポイント
この制度は、短期的な利益を追求する金融商品ではなく、経営者の将来を守るための「保険」に近い制度です。
以下の点を理解した上で、長期的な視点で活用することが成功のカギです。
- ✅長期継続が絶対条件(特に20年以上)
短期での解約は元本割れのリスクがあります。 - ✅掛金は柔軟に変更可能
月額1,000円~70,000円の範囲で、500円単位で増減できます。経営状況に応じて無理のない範囲で設定しましょう。 - ❌自由なタイミングでの引き出しは不可
老齢給付や事業の廃止など、定められた事由に該当しない限り、原則として引き出せません。
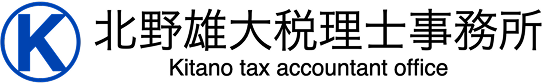
 0956-59-6590
0956-59-6590
 お問い合わせ
お問い合わせ

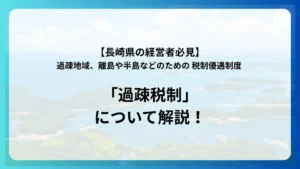
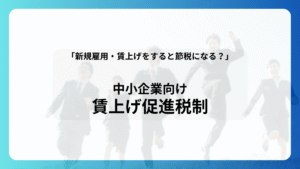
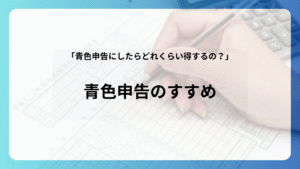
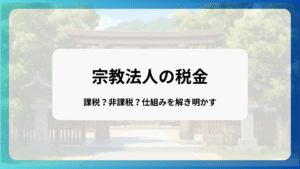

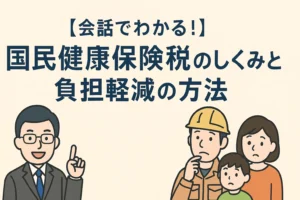
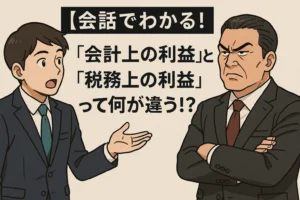
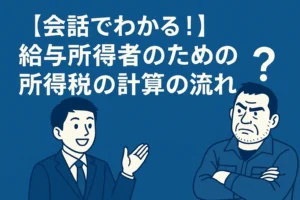
コメント