節税対策 完全ガイド
会社の利益を最大化し、未来へ投資する4つのアプローチ
王道的節税
お金の支出を伴わず、会計処理や制度活用で税金を抑える最優先の節税方法。
最小になる点を探る
法人の利益と役員個人の所得にかかる税金(所得税・住民税) および社会保険料の合計額が最小になるように、役員報酬の金額を戦略的に決定することです。 法人税率と個人の税率のバランスを考慮し、シミュレーションを行うことが不可欠です。役員報酬は事業年度開始から3ヶ月以内でなければ変更できないため、期首の段階で年間の利益を予測し、最適な金額を設定することが節税の鍵となります。
個人:非課税
法人:損金
「出張旅費規程」 という社内ルールを作成し、それに基づいて役員や従業員の出張に対して日当 (出張手当)を支給する手法です。この日当は、受け取った個人側では所得税がかからず(非課税)、支払った法人側では全額損金として経費計上できます。実費精算が難しい出張中の諸雑費を補うという名目ですが、法人・個人双方にメリットがある非常に効果的な節税策です。規程には、日当の金額、対象となる出張の定義、交通費や宿泊費のルールなどを明記し、社会通念上妥当な金額を設定する必要があります。
支払家賃 → 全額損金
受取家賃 → 益金
会社が賃貸物件を契約し、それを役員や従業員に社宅として貸し出す制度です。会社が支払う家賃は全額損金にできます。役員などから一定額(賃料の50%など、計算ルールあり)の家賃を受け取り、その金額は益金となります。役員・従業員個人が直接契約するよりも、会社負担分だけ可処分所得が増えるのと同じ効果があり、社会保険料の負担も増えません。法人・個人双方にメリットの大きい節税策です。
今期発生した費用を
→ 今期の経費に計上
決算日までにサービスの提供や商品の納入が完了しているものの、支払いが翌期になる費用を、当期の経費(損金)として計上することです。例えば、月末締めで翌月払いの外注費、従業員給与の未払分、社会保険料、水道光熱費などが該当します。支払いは先でも、発生した期の経費として計上することで、課税所得を適切に軽減できます。決算整理の際に、計上漏れがないかを徹底的に確認することが重要です。
取引先の倒産など、客観的な理由で回収が不可能になった売掛金や貸付金を「貸倒損失」として経費計上する手法です。また、取引停止後1年以上経過した場合など、法的に定められた一定の条件下では、備忘価額1円を残して損金処理することも可能です。税務上の要件は厳格であるため、内容証明郵便の送付履歴や交渉記録など、回収努力を尽くしたことを示す客観的な証拠を保管しておくことが求められます。
今期の売上
(検収基準など)
来期の売上へ
売上をどのタイミングで認識するかという会計ルール (売上計上基準)を明確にし、それに従って会計処理を行うことです。例えば、商品を販売した場合、「出荷した日(出荷基準)」「相手方が受け取った日 (引渡基準)」「相手方が検品を完了した日(検収基準)」など、複数の基準が考えられます。自社のビジネスモデルに合った、かつ継続して適用できる基準を選択することで、特に期末の売上を合法的に翌期にずらすことが可能になる場合があります。
資産価値が下落
→ 評価損として経費計上
会社が保有する商品 (棚卸資産) や有価証券などが、災害や市場の変化によって著しく価値が下落し、回復の見込みがない場合に、その価値の減少分を「評価損」として経費計上できます。ただし、税法上の要件は厳しく、「著しい時価の下落」など客観的な事実がなければ認められません。安易な適用は税務調査で否認されるリスクがあるため、慎重な検討が必要です。
帳簿価額を
全額経費に
事業に使われなくなった古い機械やPC、什器備品などを廃棄 (除却)することで、その資産の帳簿価額 (未償却残高)を全額、固定資産除却損として経費に計上します。倉庫で眠っているだけの資産を処分することで、保管スペースが有効活用できるだけでなく、帳簿上の含み損を実現させて税負担を軽減できます。実際に廃棄したことを証明する写真や、廃棄業者からの証明書を保管しておくことが重要です。
飲食費
会議費(全額損金)
交際費(上限あり)
事業関係者との飲食費は、その目的によって「交際費」と「会議費」に分かれます。「交際費」は損金にできる上限額が定められていますが、「会議費」は全額を損金にできます。社内で行う会議や、昼食をとりながらの打ち合わせなど、業務に関連する飲食は会議費として処理できます。一人あたり10,000円以下の飲食費 (社外の人が参加)も、書類を整えれば会議費として扱えます。「いつ、誰と、どこで、何のために」を明確に記録し、適切に区分することが重要です。
法人税額
控除額
政策的な目的から、特定の投資や活動を行った法人に対して、法人税額そのものから直接一定額を差し引くことができる制度です。損金算入が「課税所得」を減らすのに対し、税額控除は「税額」を直接減らすため、非常に節税効果が高いのが特徴です。代表的なものに、従業員の給与を引き上げた場合の「賃上げ促進税制」や、研究開発を行った場合の「研究開発税制」などがあります。適用要件が複雑で、年度によって内容が変わるため、自社が使える制度がないか常に情報収集することが大切です。
1年分の費用
支払時に
全額経費計上
地代家賃や保険料、サーバー利用料など、継続的なサービスに対して1年分を前払いした場合、支払った期の経費として全額を計上できる特例です。本来、費用はサービスを受けた期間に応じて按分しますが、①支払いから1年以内にサービスの提供を受ける、②毎期継続して同じ処理を行う、などの要件を満たせば、支払った時点での損金処理が認められます。決算月の利益を圧縮したい場合に有効な手段です。
投資的節税
将来の成長や収益に繋がる支出を戦略的に行い、結果として税金を抑える方法。
減価償却費を短期で計上
→ 単年度の利益を圧縮
新品ではなく中古の資産(特に車両や機械)を購入することで、法定耐用年数よりも短い年数で減価償却を行う手法です。特に4年落ちの乗用車など、一定の条件を満たす中古資産は、1~2年という短期間で償却できるため、単年度の経費を大きく計上できます。突発的に大きな利益が出た期に、将来も使える資産を導入しながら、効果的に利益を圧縮することが可能です。
未来の売上UP
決算前に利益が多く出そうな場合に、次期の売上増を見込んでWeb広告やパンフレット作成、展示会への出展費用などを前倒しで支出します。当期の利益を圧縮し税負担を軽減すると同時に、未来の顧客獲得やブランド認知度向上という「投資」になるため、非常に建設的な節税策と言えます。
企業の競争力UP
優秀な人材を採用するための費用や、従業員のスキルアップを目的とした研修費用は、全額が経費となります。これらは企業の競争力の源泉であり、長期的な成長に不可欠な投資です。節税になるからという理由だけでなく、会社の未来を創るための支出として積極的に活用すべき項目です。
従業員満足度UP
予想以上の利益が出た年度に、その利益を従業員に還元する「決算賞与」を支給する手法です。これは従業員のモチベーションを大きく向上させ、生産性アップや離職率低下に繋がる「人材への投資」と捉えることができます。決算日までに支給額を通知し、決算日から1ヶ月以内に支払うなどの要件を満たせば、支払いが翌期でも当期の損金として計上できます。
業務効率化
リスク低減
専門家(社会保険労務士など)に依頼して就業規則や賃金規程、前述の出張旅費規程などを見直し・整備する費用も経費となります。規程が整備されることで、労務リスクの低減や従業員の公平感、業務の効率化に繋がり、長期的に見て会社の生産性を高める投資となります。
リスク分散
税務メリット
新規事業を始める際に、既存の会社の一部門としてではなく、別会社を設立する手法です。これにより、新規事業のリスクを本体から切り離せるほか、法人税の軽減税率(中小企業は年800万円までの所得に適用)をそれぞれの会社で活用できる可能性があります。また、交際費の損金算入枠も別々に利用できるなど、税務上のメリットが複数考えられます。
保守的節税
万が一のリスクに備え、会社・従業員・経営者自身を守るための制度を活用する方法。
経営者の退職金
経営者や個人事業主のための「退職金積立制度」です。掛け金(月額最大7万円、年額84万円)は、法人ではなく経営者個人の所得から全額控除できます。これにより、個人の所得税・住民税が大幅に軽減されます。法人の節税ではありませんが、法人の利益を役員報酬として受け取った経営者が、手元に資金を残すために極めて有効な手段です。
取引先の倒産に備える
取引先が倒産した際に、積み立てた掛け金の最大10倍まで無担保・無保証で融資を受けられる制度です。掛け金は月額最大20万円(年額240万円)まで法人の損金として計上できます。解約時には掛け金が戻ってくる (40ヶ月以上加入で100%返還)ため、将来の資金ニーズに備えながら、実質的に費用負担なく利益を繰り延べられる効果があります。非常に人気が高く、多くの企業が活用しています。
従業員の退職金
国がサポートする従業員向けの退職金制度です。会社が支払う掛け金は全額が損金となります。福利厚生を充実させることで従業員の満足度と定着率を高め、採用活動においても有利に働くため、会社を守り育てるための投資と言えます。
福利厚生費
全ての従業員 (役員含む)を対象に、会社負担で健康診断や人間ドックを実施した場合、その費用は福利厚生費として全額損金になります。従業員の健康維持は、会社の生産性維持に直結します。「全従業員が受診できる」「会社が医療機関に直接支払う」「費用が常識の範囲内である」といった要件を満たすことが重要です。
消費的節税
事業に必要な物や従業員満足度向上のために支出し、結果として税負担を軽減する方法。
当期の経費に
事務用品やコピー用紙、インクカートリッジなど、日常的に使用する消耗品を決算前にまとめて購入することで、当期の経費として計上します。ただし、あくまで「事業に必要なものを、常識の範囲内で」購入することが大原則です。不必要に大量の在庫を抱えるような購入は、税務調査で否認されるリスクがあるため注意が必要です。
福利厚生費
従業員のリフレッシュや社内コミュニケーション活性化を目的とした社員旅行の費用は、福利厚生費として経費計上できます。税務上、経費として認められるためには、①旅行期間が4泊5日以内であること、②全従業員の50%以上が参加すること、③会社負担額が社会通念上妥当な金額 (1人10万円程度が目安)であること、といった条件を満たす必要があります。
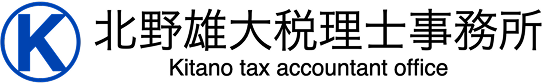
 0956-59-6590
0956-59-6590
 お問い合わせ
お問い合わせ
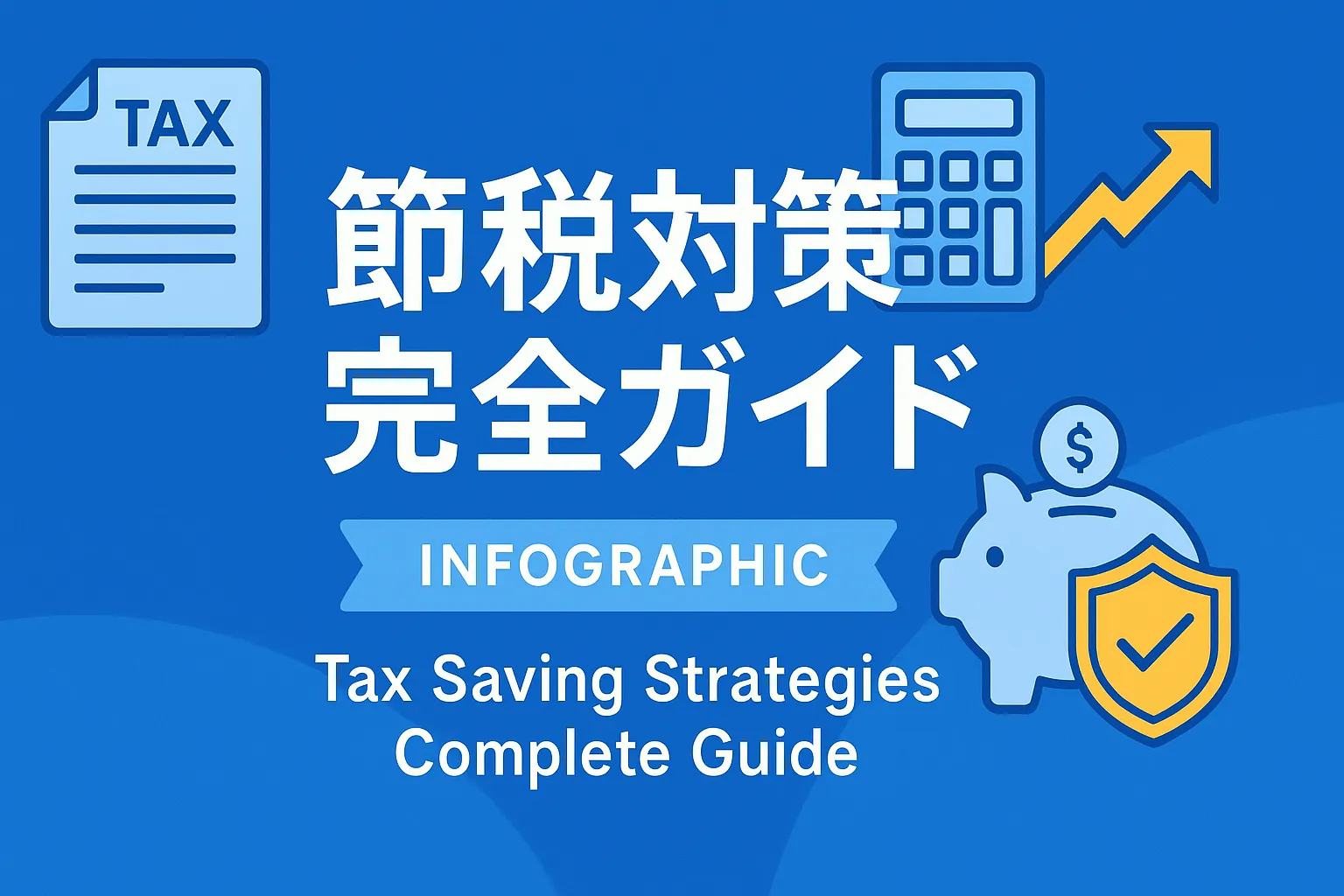
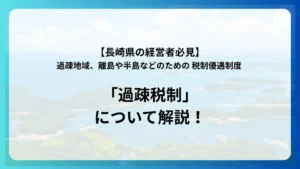
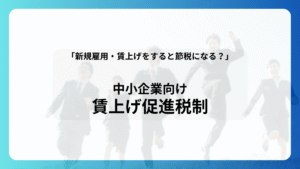
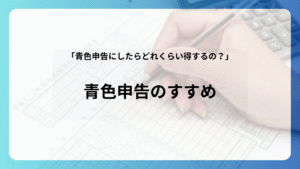
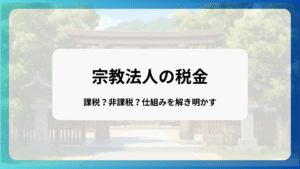

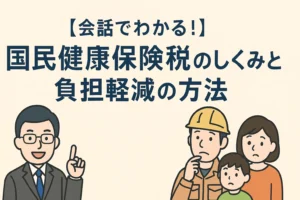
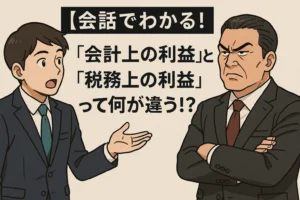
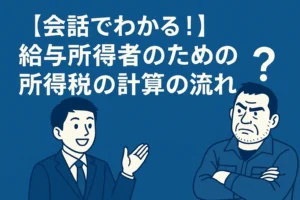
コメント