※当記事では、わかりやすさを優先し、税法上の正確性よりも日常的な言葉を優先している部分があります。
登場人物
👨💼 北野先生:やさしく丁寧な若手税理士。
👴 松木社長:口は悪いが情に厚い町工場の社長。
1. 所得税ってどうやって決まるんだ?
松木社長:
北野先生、うちの社員が「年収上がったのに手取りが減った気がする」って言ってたんだが、そんなことあるのか?所得税ってどうやって計算してるんだ?
北野:
所得税は、消費税のように本体価格に10%をかけるといったシンプルな仕組みではありません。
段階的な計算を経て、税額が決まります。
今日は、給与所得者の所得税の計算のおおまかな流れをご説明します。
2. 計算のスタートは「年収(額面)」
北野:
まず出発点になるのは「年収」、つまり会社から支払われる額面金額です。ここから最初に差し引かれるのが「給与所得控除」です。
松木社長:
それって何だ?実際に使った経費じゃないのに、引いていいのか?
北野:
たとえば、個人事業主は売上から文房具代など実際にかかった経費を差し引けます。
一方、給与所得者は経費の実費控除が原則できないため、給与所得控除という形で一律に経費相当額を引く仕組みになっています。
✅ STEP1:年収 - 給与所得控除
| 年収 | 給与所得控除額 | 差引後金額(給与所得) |
|---|---|---|
| 900万円 | 195万円 | 705万円 |
参考:給与所得控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
(国税庁 令和6年4月1日現在法令等)
3. 所得控除いろいろ
北野:
給与所得控除のあと、さらに「所得控除」と呼ばれるものを差し引きます。代表的なものは次のとおりです。
- 基礎控除:全員に適用される基本的な控除(所得が多くなると減額されます)
- 社会保険料控除:健康保険料や厚生年金などの保険料
- 扶養控除:16歳以上の扶養親族がいる場合
- 配偶者控除・配偶者特別控除:一定の要件を満たす配偶者がいる場合
- 生命保険料控除・地震保険料控除:該当する保険に加入している場合
- 寄附金控除:ふるさと納税など(年末調整では対応不可)
- 医療費控除:一定額を超える医療費がかかった場合(年末調整では対応不可)
松木社長:
なるほど、いろんな事情を考慮して、負担を軽くしてくれるってわけか。
北野:
そのとおりです。年収が同じでも扶養親族がいる場合といない場合では、かかる所得税の額は異なります。
なので、「年収が〇〇円なら、所得税はいくら」と一律に決まっているわけではないのです。
✅ STEP2:給与所得 - 所得控除
例)年収900万円の人で下記条件の場合
- 社会保険料:127万円(年収のおおよそ15%ほどで試算してみてください)
- 扶養控除(大学生の子が1人):63万円
- 生命保険料控除(新生命保険に年間12万円支払っている):4万円
- 基礎控除:58万円
計算:
705万円(STEP1の額)- 127万円 - 63万円 - 4万円 - 58万円
= 453万円(課税所得)
4. 所得に税率をかける
北野先生:
こうした控除をすべて差し引いた後に残るのが「課税される所得」です。これに対して、所得税率表を適用して税額を計算します。
【令和7年現在の所得税の速算表(抜粋)】
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
所得税率:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm(国税庁HP)
松木社長:
ってことは、所得が900万円を超えたら全額に33%がかかるわけじゃないんだな?
北野先生:
おっしゃる通りです。超えた部分にだけ高い税率がかかる「超過累進税率」ですので、全体の税率が一気に上がるわけではありません。
✅ STEP3:課税所得 × 税率 - 控除額
例)課税所得:453万円(STEP2の額)←上記の表に当てはめると3,300,000円 から 6,949,000円までのライン。
→ 税率:20%、控除額:427,500円
→ 4,530,000円 × 20% - 427,500円 = 478,500円
5. 源泉徴収と年末調整
北野先生:
会社員は毎月のお給料から所得税が源泉徴収されています。これは国が定めた「源泉徴収税額表」に基づいて計算されています。
松木社長:
うちでも毎月きっちり引いてるぞ。
北野先生:
年末には、1年分の所得や控除を再計算して正確な税額を出します。これが「年末調整」です。
源泉徴収された金額が多ければ還付、少なければ追加で徴収されます。
✅ 還付・徴収の仕組み(例)
| 月々の源泉徴収 | 年間合計源泉徴収 | 実際の所得税(STEP3の額) | 差額(還付) |
|---|---|---|---|
| 5万円 | 60万円 | 47.85万円 | 12.15万円 |
※上記の源泉徴収額は仮の数字です。
また、所得税は実際には復興特別所得税(2.1%)の加算もあり、厳密な計算とは異なりますがおおよその流れは上記の通りです。
松木社長:
ふるさと納税とか医療費控除は?
北野先生:
それらは年末調整では対応できないので、別途確定申告が必要です。ふるさと納税はワンストップ特例制度の利用も可能です。
6. 「年収が増えると手取りが減る」は本当?
北野先生:
「年収○万円を超えると手取りが減る」という噂はよくありますが、基本的には誤解です。
所得税は超過累進課税なので、年収が増えても手取りが減ることは通常ありません。
松木社長:
じゃあ、昇給しても安心ってことか?
北野先生:
ただし、一部の控除(たとえば基礎控除)は、所得が一定以上になると減額され、最終的には適用されなくなることがあります。
その場合、増えた収入に対して増える税額の方が多くなる可能性があり、結果として手取りが減るケースもありえます。
最後に:「応能負担の原則」
北野先生:
日本の税制は「応能負担」、つまり税金は“払える能力に応じて”負担するという考え方です。
生活や家族構成によって控除があり、税率も段階的に上がる仕組みです。
松木社長:
なるほどな。一律じゃない分、少し複雑なんだな。まあ簡単じゃないから税理士の出番ってわけか。
北野先生:
その通りです。お気軽に、いつでもご相談ください!
弊事務所の対応地域
訪問可 :長崎県佐世保市、佐々町、旧北松地区、松浦市、平戸市
オンライン:全国
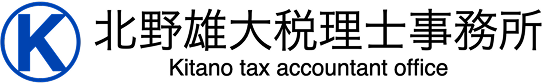
 0956-59-6590
0956-59-6590
 お問い合わせ
お問い合わせ
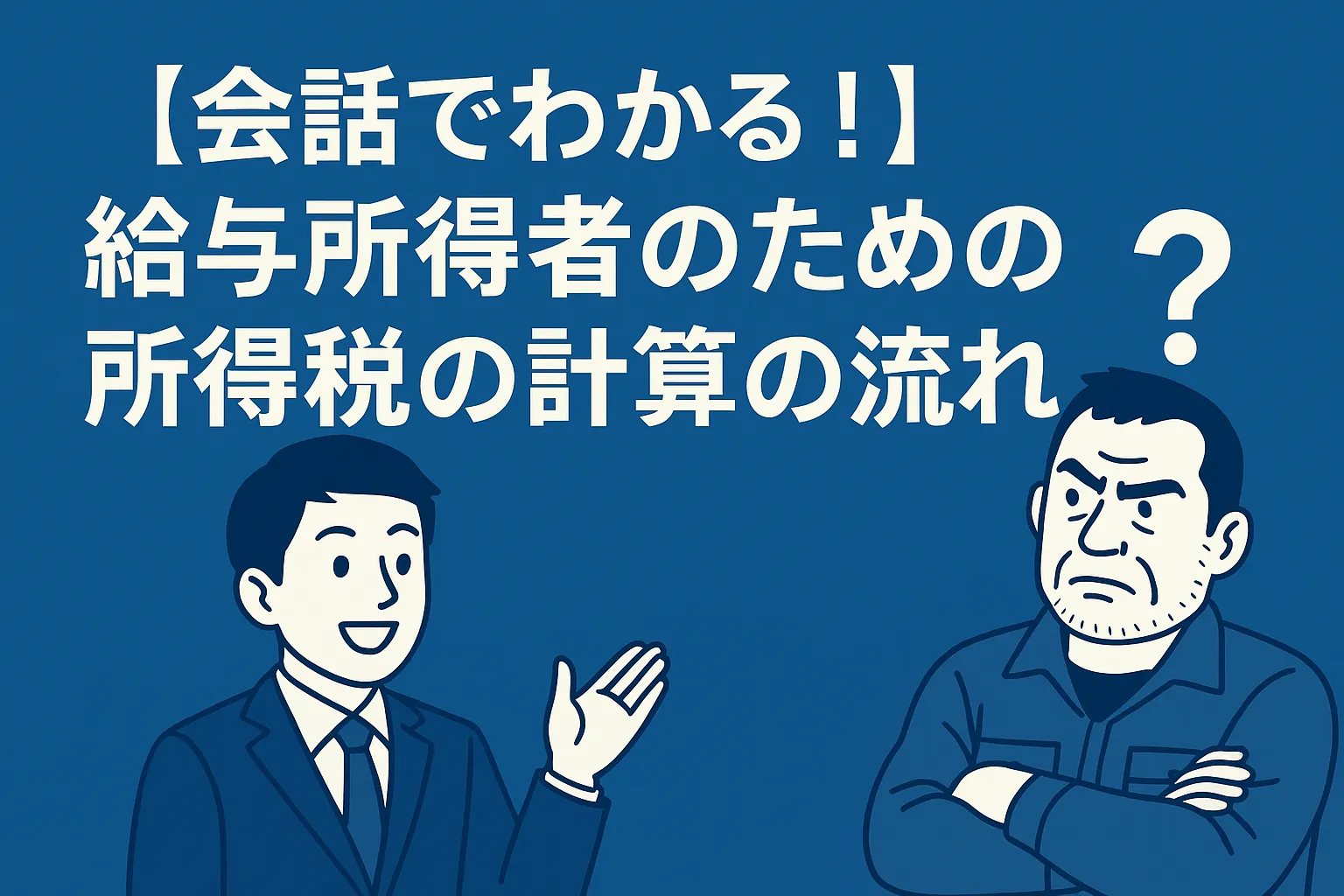
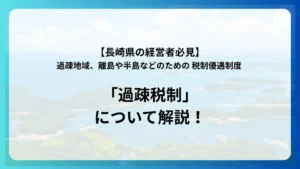
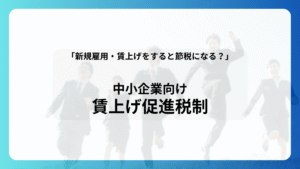
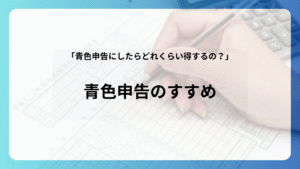
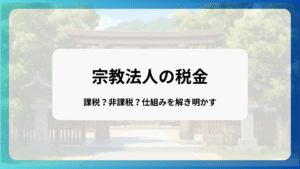


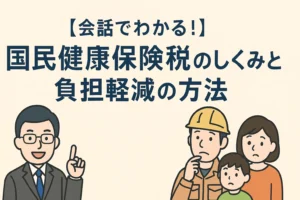
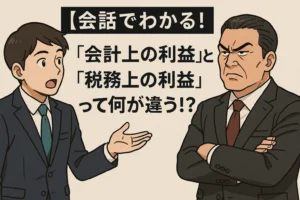
コメント