皆さん、こんにちは!北野税理士事務所の税理士、北野です。
今日は、多くの個人事業主の皆様が頭を抱える「国民健康保険税」についてその「算出方法」「国保負担軽減の方法」について解説します。
「どう計算されてるのかわからない」
「負担が大きいけど、減らす方法なんてあるの?」
そんな疑問をお持ちの方に向けて、今回は45歳の一人親方・山田さんとの会話を通じて、
国民健康保険税のしくみや、負担軽減のヒント、世帯分離の効果までわかりやすくお伝えします!
登場人物
- 北野 :北野税理士事務所の税理士。丁寧な口調が持ち味。
- 山田さん:45歳の一人親方。妻(43歳)と未就学児2人の4人家族。
「国民健康保険税って、結局なんなんですか?」
山田さん:北野先生、毎年6月ごろに来る国保税、負担が重いです・・。あと正直どう計算されてるのかさっぱりです…。
北野:たしかにわかりにくいですよね。では、本日はそのあたりについて解説いたします。
まず、国民健康保険税とは、国民健康保険に加入している人が市区町村に払う保険料のことです。
職場の健康保険などに加入している人、後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人以外は、国籍を問わず、すべての人に加入が義務付けられています。
「誰が払う義務があるんですか?」
山田さん:じゃあ、自営業の人は全員払うってことですか?
北野:そうです。主に自営業、フリーランス、無職、年金生活者(後期高齢者医療制度に加入している75歳以上の人を除く)などで会社に勤めていない人が対象ですね。保険税は世帯ごとにまとめて計算され、世帯主が支払うことになります。たとえ世帯主自身が国保に加入していなくても、世帯内のどなたかが加入していれば、世帯主が納税義務者となります。
余談ですが、「国民健康保険税」も「国民健康保険料」も基本的には同じものです。
市町村の選択により、保険「料」の形式を採る以外に、徴収上の便宜として保険「税」の形式を採ることが認められています。
聞いた話では「保険料」と表記するよりも「保険税」と表記したほうが、未納が減るそうです。
「どうやって計算されてるんですか?」
北野:国民健康保険税は、次の3つの要素で構成されます。
- 所得割:前年の所得に応じて計算されます。所得が高いほど税額も高くなります。
- 均等割:国民健康保険の加入人数に応じて定額が課税されます。
- 平等割(世帯割):1世帯ごとに定額が課税されます。
この3つの要素を、それぞれ以下の3区分で計算して合計します。
- 医療分:医療費の給付などに充てられる基本的な部分です。
- 後期高齢者支援分:後期高齢者医療制度を支えるための費用です。
- 介護納付金分:40歳から64歳までの人が対象で、介護保険制度を支えるための費用です。
「じゃあ、うちみたいな4人家族だと、いくらくらいになるんですか?」
北野:では実際に試算してみましょう。
【試算】山田さん一家(4人家族・佐世保市)のケース
条件:
- 山田さん:45歳、事業所得600万円(前年の利益(控除前所得)から青色申告特別控除額65万円を引いた額)
- 妻:43歳、所得なし
- 子ども:6歳・3歳(ともに未就学児)
- 全員国民健康保険に加入
1. 課税対象所得の算出
国民健康保険税の所得割の計算に用いられる所得は、前年の総所得金額から基礎控除43万円を差し引いた金額です。
6,000,000円(事業所得)- 430,000円(基礎控除)= 5,570,000円
2. 各区分の計算(令和7年度・佐世保市) 佐世保市の令和7年度の税率・金額をもとに計算します。
| 区分 | 所得割額(算出) | 均等割額(人数分) | 平等割額(世帯) | 合計(限度額適用前) | 限度額 | 適用される税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 5,570,000円 × 8.0% = 445,600円 | 24,600円 × 4人 = 98,400円 | 18,000円 | 562,000円 | 660,000円 | 562,000円 |
| 後期高齢者支援分 | 5,570,000円 × 3.4% = 189,380円 | 10,600円 × 4人 = 42,400円 | 7,300円 | 239,080円 | 260,000円 | 239,080円 |
| 介護納付金分 (※) | 5,570,000円 × 2.8% = 155,960円 | 10,600円 × 2人 = 21,200円 | 5,000円 | 182,160円 | 170,000円 | 170,000円 |
※介護納付金分は、山田さん(45歳)と妻(43歳)の2人が対象です。お子さんは対象外です。
✅ 年間国民健康保険税額の合計
医療分(562,000円) + 後期高齢者支援分(239,080円) + 介護納付金分(上限適用後170,000円) = 971,080円
北野:各区分に上限額が設定されているため、合計額が上限に達するとそれ以上は課税されません。国民健康保険税全体の賦課限度額は、令和7年現在では、109万円です。仮に所得が1,000万円で他の条件が上記と同じだった場合、国民健康保険税は109万円になります。
「世帯分離って、やったほうが得なんですか?」
山田さん:この間、知り合いに「世帯を分けたら国保が安くなるかもよ」って言われたんですけど…
北野:条件によってですが、世帯分離で負担が下がるケースもあります。また、場合によっては世帯を同じにした方が全体の負担が下がるケースもあります。
■世帯分離で負担が下がるケース
「世帯の所得金額(世帯主の所得+世帯主以外の加入者全員の所得)」が軽減判定基準額以下の場合、均等割額と平等割額を軽減する制度が設けられています。
仮に所得がゼロの奥様を別世帯とした場合、奥様世帯は住民税非課税世帯となります。
奥様世帯に対しては、軽減措置が適用可能となり、均等割や平等割が7割・5割・2割などに軽減され、未就学児にかかる軽減も適用されます。
| 軽減判定基準額 | |
| 7割軽減 | 43万円+(10万円×(給与所得者等数(※)-1)) |
| 5割軽減 | 43万円+(30.5万円×加入者数)+(10万円×(給与所得者等数(※)-1)) |
| 2割軽減 | 43万円+(56万円×加入者数)+(10万円×(給与所得者等数(※)-1)) |
※給与所得者数(以下の①、②、③いずれかの要件を満たす方の合計人数)
①給与収入で55万円を超える方
②公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または125万円を超える65歳以上の方
③上記①、②の両方に該当する方
■世帯を同じにすることで負担が下がるケース
逆に世帯を同じにすることで、全体の負担が下がるケースもあります。
国民健康保険税は世帯ごとに負担額の上限額(令和7年の場合、上限109万円)がありますので、
仮にA世帯とB世帯がそれぞれ100万円の国保税を支払っていた場合(100万円+100万円=200万円)、世帯を同じにすることで、全体の負担を下げる(上限109万円)ことが可能です。
■要点
・2つの世帯のうち1つが「所得の低い世帯への軽減措置」を受けられる場合 → 世帯分離を検討
・2つの世帯がそれぞれ高額な国民健康保険税(個々の世帯の賦課限度額に近い、または超えている)場合 → 世帯を同じにすることを検討
【注意】世帯分離には「生計が別であること」が原則
山田さん:でも先生、住所が一緒でも住民票だけ世帯を分けるなんてことをしてもオッケーなんですか?
北野:ここが重要なポイントです。たしかに住民票上の世帯を分ければ「世帯分離」自体はできますが、自治体によっては保険料の軽減措置を受ける際に、「形式的な分離」ではなく、実質的にも“生計が別”であることが必要とされているケースがあります。山田さんの場合は、生計が同じかと思われますので、世帯分離をすることは推奨しません。
🔎 コラム:世帯分離の注意点
国民健康保険税の軽減措置(非課税世帯の判定など)においては、「居住が同じでも、生活費・家計の管理が独立しているかどうか」が重要視されることがあります。
例えば、夫が一家全体の生活費を負担している場合、たとえ世帯を分けても「同一生計」と見なされる可能性があります。また、税務署や自治体が「意図的な節税目的の形式的分離」と判断した場合、軽減措置が適用されないこともあります。世帯分離は住民票上の手続きですが、その実態が伴わない場合、行政サービスの利用において不都合が生じる可能性や、場合によっては不正受給とみなされるリスクも考慮する必要があります。
北野:ですので、「世帯分離すれば誰でも保険料が安くなる」という風に断言はできません。実際に生活費を分けているか、家計管理が独立しているかどうか──ここが非常に大事です。
山田さん:なるほど…。分けりゃ得ってもんじゃないんですね。ちゃんと正直に生活スタイルに合った判断が必要ですね。
北野:おっしゃるとおりです。
負担を軽くするその他の方法は?
北野:国民健康保険税の負担を軽減するための方法は、世帯分離以外にもいくつかあります。
■課税対象所得を減らす
・適切に経費を計上し、所得を減らす(脱税はNG!)。
・経営セーフティ共済に加入する。
・青色申告+電子申告で65万円控除を適用する。
■健康保険組合に入ることを検討
・医師、歯科医師、薬剤師、弁護士、税理士、理・美容師、建設業界、食品業界など、様々な業種の国保組合があります。
・国民健康保険とは別の業界の組合保険に入ることで、保険料を安くすることができるケースがあります。
■マイクロ法人スキーム
・法人を設立し、国保をやめて法人の社会保険に加入します。
・社会保険料の計算基礎となる自身の役員報酬額を低く設定し、保険料の負担を軽減しようとするのが、いわゆる「マイクロ法人スキーム」です。
※マイクロ法人スキームの落とし穴とリスク(重要!)
●社会保険料の増加リスク・・・そもそも社会保険は、国民健康保険よりも高額になることが一般的です。適切に役員報酬を設定しなければ、かえって負担が増える可能性もあります。
●法人設立と維持のコスト・・・法人を設立するためには、登記費用や専門家への相談料、さらに法人維持にかかるコスト(会計や税務申告のための費用)も発生します。
●税務上の問題・・・一部の業務を法人に移し、他の業務は個人事業として残すといった分割は、税務署に「不自然な所得分配」と判断される恐れがあり、税務調査の対象になるリスクも考慮しなければなりません。法人化の目的は「信用力の向上」や「事業発展のため」及び「管理運営上のため」といった整理が必要です。
●将来的な影響・・・保険料の負担を減らすことは、将来的には年金受給額の減少や医療保険の範囲に影響を与える可能性があります。
●規制の可能性・・・「このスキームは不適切」として将来的には規制が入る可能性もあります。いろいろな意見がありますが、現時点(R7.6時点)では合法です。
▼そのほかにできること
- 所得の申告を忘れずに!
前年の所得が一定基準以下の世帯は、均等割や平等割が減額される制度があります。この軽減措置は、所得の申告をしていることが条件です。所得がなかった場合でも、必ず確定申告や住民税の申告を行いましょう。無申告だと軽減対象になりません。 - 未就学児の均等割は半額
令和4年度から、未就学児(小学校入学前の子ども)の国民健康保険税の均等割額が、自動的に半額に軽減される制度が導入されています。 - 非自発的失業者は軽減制度あり
会社の都合や倒産などで離職した方(特定受給資格者・特定理由離職者)は、失業期間中の国民健康保険税が軽減される場合があります。ハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」に記載される理由コードが対象となります。 - 産前産後は軽減制度あり
出産された(される)方、妊娠85日(4か月)以上の出産が対象(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)は、申請により軽減が可能です。必要書類:母子健康手帳など出産予定日が分かるもの - 災害や大幅な収入減少時には減免申請を
災害や病気、失業などにより、一時的に収入が著しく減少した場合など、特別な事情がある場合には、申請により保険税の減免を受けられることがあります。お住まいの自治体にご相談ください。
まとめ
✅ 国民健康保険税は「所得割・均等割・平等割」の合計で計算される!
✅ 令和7年度の国民健康保険税全体の賦課限度額は原則109万円!
✅ 世帯分離で国保の負担が軽減される場合もあるが、「生計が別」であることなど条件に注意が必要!
✅ 青色申告、電子申告の活用・自身の状況に応じた軽減の申請・各種減免制度の活用も重要!
弊事務所の対応地域
訪問可 :長崎県佐世保市、佐々町、旧北松地区、松浦市、平戸市
オンライン:全国
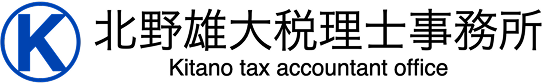
 0956-59-6590
0956-59-6590
 お問い合わせ
お問い合わせ

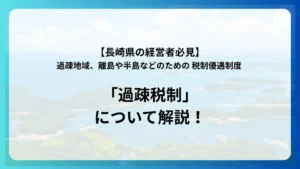
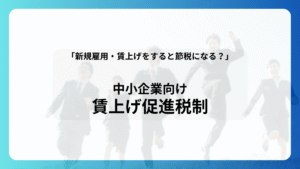
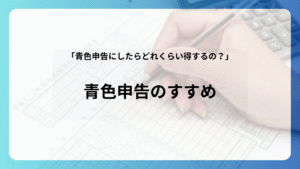
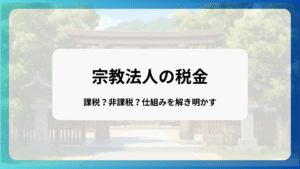


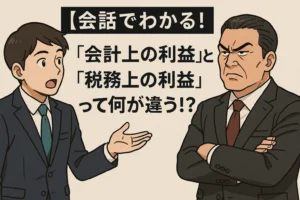
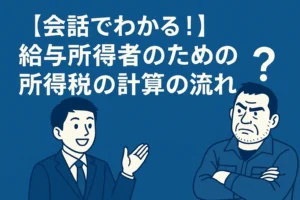
コメント