「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」
――税理士法 第一章 第一条
税理士法の条文にある通り、税理士は税務の専門家だ。
だが近年、旧来の税理士業務だけでなく、すそ野を広げて顧客を支援しようと考える税理士が増えている。
「従来の税理士業務だけでは生き残れない!」という危機意識から、「“これからはITで効率化”,“コンサルティングによる支援”を差別化要素として展開していこう。」こういった思考回路を辿るのが、あるあるだ。
何を隠そう、私もご多分に漏れず、そのような思考回路を辿っている税理士のうちの一人である。
HPに記載の通り、私自身、“ITによる効率化”や“財務コンサルティング”をサービスとして提供しているのだが、
正直なところ自分で「わたくしコンサルタントをやってます」と言うのはどこか面映ゆいような気がするものである。
「コンサル」と聞くと、どうしても
- 言うだけ言って責任は取らない
- アドバイスしたら仕事終了
- 名乗れば誰でも今日からコンサル
…といった負のイメージが頭をかすめるからだ。
帝国データバンクによれば2024年の経営コンサルタント業の倒産は154件。
過去最多を更新し、「自称・経営のプロが倒産してどうする」という状況である。
(もちろん本物の尊敬すべきコンサルタントも多く存在する。)
また、「財務コンサル」と「経営コンサル」は別物だと私の中では整理しているのだが、顧客の目には同じようなものに映るだろう。
というわけで、「財務コンサルティング」というサービスを提供するにあたって、開業前に私は以下のようなことを自問自答した。
- 他のコンサルを名乗るライバルに負けないだけの知識が本当にあるか?
- 御用聞きで終わらず、能動的に提案ができるか?
- 施策の効果を数字で検証し、言いっぱなしにしないか?
熟考の末、「やるなら徹底的にやろう」と腹をくくった。
さて、その上でさらに思考を進めた。
税理士がコンサルティングを行うとき、最大の足かせは損害賠償リスクである。
「税務調査で否認されたら?」「提案のせいで資金繰りが悪化したら?」――そんな恐れから、多くの同業者が自分の意見を言わず、
「それは経営判断になりますので……」
と一歩引いてしまっているのではないだろうか。
実際、私も「それは経営判断になりますね」というセリフを使ったことがある。
経営判断であることは事実なのではあるが、その瞬間、心の中で――
(うわ~今おれ経営判断に逃げたなあ)と猛省することとなった。
損害賠償までいかずとも「君の言うとおりにやったら損をしたじゃないか!」とお叱りを受けることもあるだろう。
それでも財務コンサルタントを名乗るのであれば、「経営判断になります」として逃げず、自分の意見を言うことが必要である。
たとえば役員報酬の設定。
本来、社長が役員報酬をいくらに設定するかというのは、税理士が口を出す領域ではないが、財務コンサルとして関与するなら以下のような答えも用意しておくべきだ。
「税額シミュレーションの結果、年額●●円が最も税負担を抑えられます。
ただし、将来の退職金や株価評価にも影響するため、次の3点を念頭に置きましょう。
① 退職金の損金算入枠
② 相続・事業承継時の株価
③ 社会保険料負担とキャッシュフロー
(ついでに言うならば、役員報酬増加によって所得税の負担は増えますが、その分個人資産が増えるので、その資産運用による利回りも含めて検討したいところです。もちろんライフプラン(将来家を買うかといった個別の事情)も考慮しなければなりません。)
さまざまな情報をヒアリングして試算したのち、リスクを説明したうえで“私の意見はこれです”と明言する。
そこで初めて、社長は真に経営判断を下せるのだと思う。
ーーーーーーーーーーーーー
北野税理士事務所は、言いっぱなしで終わらない財務コンサルティングで経営者のみなさまの意思決定を後押しします。
ぜひ一度、ご相談ください。
弊事務所の対応地域
訪問可 :長崎県佐世保市、佐々町、旧北松地区、松浦市、平戸市
オンライン:全国
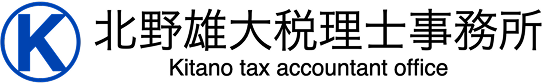
 0956-59-6590
0956-59-6590
 お問い合わせ
お問い合わせ
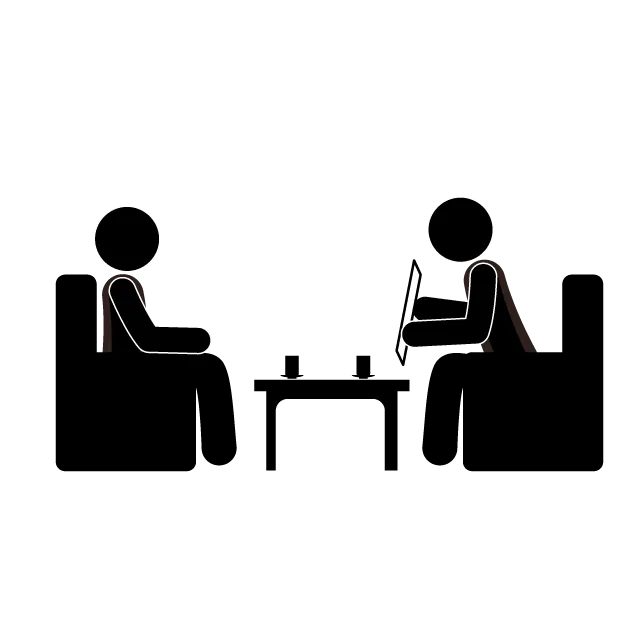
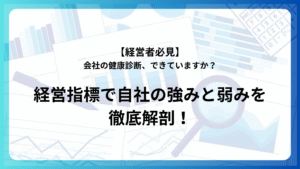
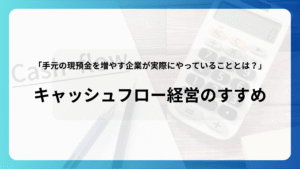

コメント